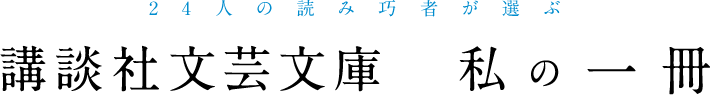優しさと冷酷さ
このエッセイのために、久しぶりに各短編を読んでみた。だが、今読み返すと、何かが違う気がした。何なのか、最初わからなかった。南紀州の無頼の男と流れ者の女の性行為が執拗に描かれる、という風に評されている。だが「南紀州」ではなく「近畿・紀伊半島南部地方」と記すと印象が違ってくる。「無頼の男」だと、どことなくかっこいいが、「低学歴の肉体労働者」「貧困層」などと表現すると、インパクトがなくなる。「流れ者の女」だと、訳ありの艶っぽい女が目に浮かぶが、「無職・住所不定でセックス依存症の女」と記すと、精神が不安定で貧相な女を想起してしまう。さらに「性行為」ではなく、今風に「エッチ」だと、『水の女』の衝撃は完全に違うものに変質する。
違和感の正体は、中上健次が描き出した世界はもう存在しないということだった。ただし、だから作品として価値が薄れるということではもちろんないし、また、消滅した世界だから後世に残すという新しい価値が生まれるというわけでもない。『水の女』は、時代に関係なく「自律」して存在している。性行為の描写は独特で、冷酷な印象もあるし、優しさも感じる。登場人物たちの行為は「エッチ」ではないし、「セックス」とも違う気がする。中上健次は「交接」という言葉を使っているが、問題の核心は、性行為を表す言葉ではない。「冷酷さ」と「優しさ」が溶け合っていて判別がつかない性愛、それが『水の女』の最大の魅力だということだ。
最初に読んだとき、畏怖の念に打たれた。すごいと思い、こんな小説は自分には絶対に書けないと、打ちのめされたような気分になった。だが、しばらくすると、自分もこういう小説を書いてみたいと思うようになった。「こういう小説」というのは、冷酷さと優しさが溶け合って、精神の「闇」が魅惑的に浮かび上がってくる、そんな作品だ。まったく別の方法論、文体で書こうと決めて、数年後、わたしは『トパーズ』という連作短編を書きはじめることになる。
村上 龍
作家。主な著書に『限りなく透明に近いブルー』『愛と幻想のファシズム』『トパーズ』『半島を出よ』『歌うクジラ』など。
水の女
中上健次 ●定価:本体1200円(税別)