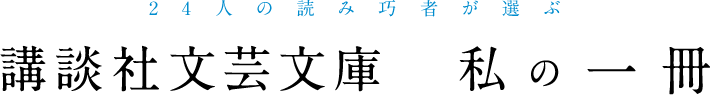句読点のあじ
文芸作品を読む楽しみは、主題や作者の情意にかかわらず、一文の一語や句読点へ迷い込み、想像を巡らすことにある。表題作の主は屋台のおでん屋、末吉四十五歳。女房に先立たれ、三つの娘おしづと四畳半一間に暮らす。末吉の日日の糧、おしづとの間合いが楽しい。好きな一文は、おしづを寝かしつける末吉の目が棚の麦藁帽子に止まる件。「お目めをつぶってごらん。ほら、大きい象さんが見えるよ。」添寝する末吉の目差に帽子の鍔は見えぬ、頂が象に見えた。「お目めをつぶってごらん。」は、子供相手の手品の呪文、ちちんぷいぷい。象が消えぬよう己に掛けた呪文でもある。で、「ほら、」の読点。明朝体の読点は左上の起筆から右下への筆跡をとどめてある。一画の右上に入る読点の余白が左の行間に溢れ、読者の目を迷わす。おしづの目差を棚へ導く末吉の指先が余白に浮かぶ。末吉の日日に力をもたらすのは、保育園の送り迎えで引くおしづの手の感触、銭湯の湯へ抱き入れる静もった肌の触感。麦藁帽子の前の件は、おしづの腹や背の疣で医者へ連れて行く。気付いたのは湯の中。見つめた疣と帽子の頂が、棚の上で一つになった、象の幻。鉤括弧の隙間から、おしづの唄うぞうさんの一語が聴こえた。見つめた句点がおしづの小さなお口に見える。
菊地信義 Kikuchi Nobuyoshi
装幀家。講談社文芸文庫の装幀を創刊時から手がける。装幀の業績で藤村記念歴程賞、講談社出版文化賞受賞。著書『装幀の余白から』、装幀集『菊地信義の装幀』など。