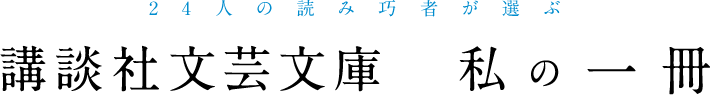欠落の小説
病気の娘、稲子を入院させた母親と稲子の恋人久野が、帰りがけ、汽車に乗る筈が、いま入院させたばかりの稲子を明日にでもとりもどしたいという久野の発案で、町の宿に泊る。稲子の病気は、目の前にいる相手の体が見えなくなる、人体欠視症。久野は稲子のその症状が、愛している相手にしか起らないと考え、それならいっそ結婚しようとまで思っている。結婚すれば稲子は治る、と。病院は寺の境内にあり、入院患者がつくらしい鐘の音が、宿にいる二人にも聞えてくる……
どうもよく分らない、摑みづらい小説だ。人体欠視症というのは、この作品を書くにあたって作者が作った架空の病気だと思われる。そのため読者はこの病気を、リアリティをもって思い描くことが出来ない。しかもその患者を眼科や内科でなく精神科に入院させるとは、いったいどういう判断によるのか。
だが川端康成の目と筆はそういう読者の常識を置き去りにして、二人の会話を延々と進めてゆく。つまり、人体欠視症の稲子自身は物語に登場せず、ただ二人の回想によって語られるだけ。まるで稲子が死者であるか、あるいは母と久野が、そして読者が、稲子欠視症にでもなってしまったかのようだ。見えるとは、見えないとは、いったいどういうことであるのか。その場にいない、またいないように見える人物こそがもしかすると一番重要なのではないか。極端に言えばいない人物を想像することによってのみ、ここにいる母や久野、さらに我々も、何かを思い、言葉を発しているのではなかろうか。存在しない存在、いないのに確かにいる誰かに向って書くのが小説、作家としてはそうも感じる。
作品は作者の死により未完となっている。書かれなかった部分はひょっとすると、入院中の稲子が登場する展開になっていたかもしれない。稲子の不在と作品の未完。『たんぽぽ』は永遠の欠落に支えられた小説だ。
たんぽぽ
「人体欠視症」という奇病に冒された娘をめぐる狂気、不可思議な愛のかたち。
『眠れる美女』『片腕』の後に執筆、その死で中断された川端康成最後の連載小説。
川端康成 ●定価:本体854円(税別)
田中慎弥
作家。「冷たい水の羊」でデビュー。「蛹」で川端康成文学賞、『切れた鎖』で三島由紀夫賞、「共喰い」で芥川賞受賞。他の作品に『燃える家』『宰相A』など。